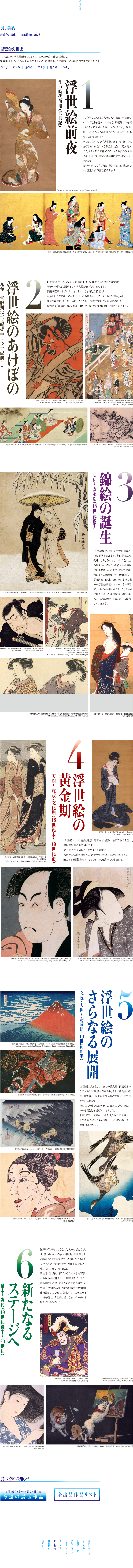
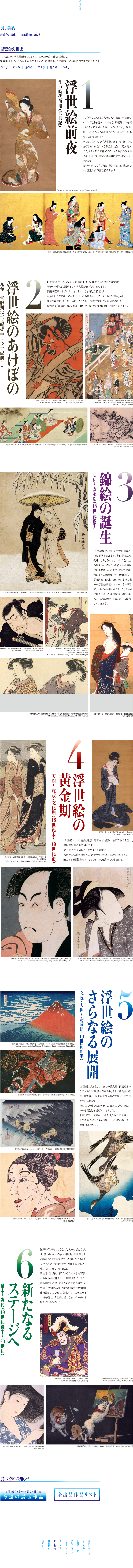
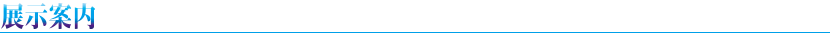

70人以上の浮世絵師たちによる、およそ350点の作品を通じて、
300年以上にわたる浮世絵全史をたどる、本展覧会。その構成と主な出品作品をご紹介します。
江戸時代に入ると、人々の人生観は、明日をも知れぬ現世を憂うのではなく、積極的に今を楽しもうとする気風へと変わっていきます。「浮世絵」とは、そんな“浮き世”の今、最新流行の風俗を描いた絵のこと。
そのはじまりは、寛文年間(1661–73)を中心に流行した、女性1人を独立して描く“寛文美人図”、さらにその母体である、人々の営みや風俗に注目した“近世初期風俗画”まで辿ることができます。
第一章では、こうした浮世絵の誕生に至るまでの、貴重な肉筆画を紹介します。

![]()
17世紀後半ごろになると、絵師が1枚1枚直接描く肉筆画だけでなく、
冊子や一枚物の版画として浮世絵が刊行され始めます。
版画は庶民でも手に入れることのできる身近な絵画として、
次第にひろく普及していきました。その色合いも、モノクロの「墨摺絵」から、
鮮やかな朱色(丹)を手彩色した「丹絵」、植物性の紅など淡い色合いを
数色摺る「紅摺絵」など、およそ100年をかけて徐々に進化を遂げていきます。
18世紀末には、清長、歌麿、写楽など、優れた絵師が次々と現れ、浮世絵は黄金期を迎えます。
美人画や役者絵はこれまでよりも大型化し、
当時の人気を集めた美人や役者たちの姿を生き生きと描きだす
迫力ある画面となって、さらなる人気を高めてゆきました。
|
|
|
江戸時代が終わりを告げ、人々の感覚が大きく変わろうとする幕末明治期、浮世絵もまた模索のときを迎えます。時事世相や新しい文物へとテーマは広がり、西洋的な表現も取り入れられていきました。 |
|
