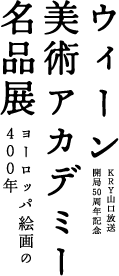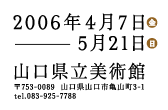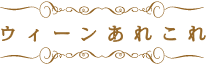展覧会をより楽しむために、ウィーンの文化や歴史にまつわるエピソードや、関連書籍などを紹介します。
本展覧会の顔として活躍していただいている、女帝マリア・テレジア。目の大きな愛らしい顔はもうおなじみですが、一体どんな人だったのでしょう。ここでは、彼女や、彼女を生んだハプスブルク家についてお話します。
ハプスブルク家とは
1200年代の終わりから1900年代の初めまで、主にオーストリアを支配した名門王家。16世紀のカール五世の時代は、オーストリア、ハンガリー、チェコ、オランダ、ベルギー、スペイン、イタリアの一部にまで同家の支配がおよんでいました。その後、同家はオーストリア系とスペイン系に分裂し、スペイン系は断絶してしまいます。オーストリア系ハプスブルク家によるオーストリア周辺地域への統治は、第一次世界大戦の終了後まで続きました。
名君マリア・テレジア
そんなハプスブルク家きっての名君がマリア・テレジア(1717-1780)です。父親のカール6世に男の子がいなかったので、長女の彼女がすべての領土を相続し、オーストリア大公となりました。
即位23歳
オーストリアの君主になったとき、マリア・テレジアはわずか23歳。すでに3人の子を生み、4人目をみごもっていました。「ふん、あんな小娘。すこしくらい、領土をぶんどってもいいだろう!」隣国プロイセンのフリードリヒ大王は、あっという間にオーストリアに攻めこみ、シュレージエン地方を占領してしまいます。「シュレージエン泥棒!」テレジアは大いに怒り、反撃を開始。プロイセンとの二度にわたる大きな戦争をたたかいぬき、フリードリヒ大王をふるえあがらせました。奪われた領土はついに取り返せなかったものの、もう誰も「小娘」などと言いません。マリア・テレジアは、ハプスブルク帝国君主としての力を十分に示したのです。
おしどり夫婦
ちなみに、マリア・テレジアは、当時としては大変めずらしく恋愛結婚をしています。夫は、9歳年上のロートリンゲン公フランツ・シュテファン。5歳で恋におちたテレジアは、19歳で初恋をみのらせて結婚。夫との間になんと16人の子どもをもうけました。(そのうち、親よりも長生きしたのは10人でした)フランツが亡くなってからは、悲しみのあまり、生涯、喪服を脱がなかったと言われています。
©The Yamaguchi Prefectural Museum of Art